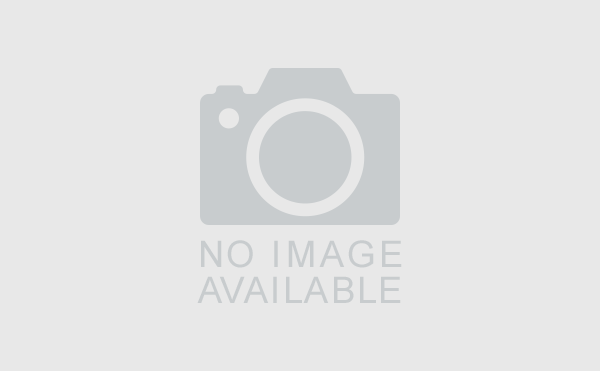原価計算の手順と製品別原価計算方法の種類
工場で発生した様々な製造原価は、次の手順により、製品ごとに集計されます。
① 費目別計算→②部門別計算→③製品別集計 なお、③製品別集計の手順は、製品の生産形態によって、「個別原価計算」と「総合原価計算」とに大別されます。
費目別計算
製品の製造のために発生した様々な製造原価を材料費、労務費、消耗品費などの原価要素(費目)ごとに集計します。なお、企業会計では、「勘定科目」を用いて費目の集計を行っているため、「製造原価報告書」では、これらの原価要素が、勘定科目ごとに表示・集計されています。
部門別計算
費目別に集計した製造原価を、製造部、資材部、生産管理部、品質管理部などの工場の各部門別に集計します。また、工場の各部門のうち、製造作業に直接携わる部門を「製造部門」といい、材料の管理など、製造作業に直接携わらず、製造作業を補佐する部門を「補助部門」といいます。
なお、工場の組織を部門別に分けていない場合、部門別計算は省略します。
製品別集計
費目別・部門別に集計した製造原価を、製品ごとに集計します。なお、製品の生産形態によって、「個別原価計算」と「総合原価計算」のいずれかの方法によって計算します。
個別原価計算
個別原価計算は、異なる種類の製品をその都度生産する場合に用いられます。受注生産方式の製造業、建設業、ソフトウェア製作企業に向いている原価計算方式です。個別原価計算では、製品や案件ごとに原価の集計単位を設定し、材料費・労務費・製造経費を集計します。なお、完成原価と仕掛高の区別は、原価の集計単位とした製品の製造が完了した場合や、案件で行う作業がすべて完了した場合は完成原価(売上原価)となり、未完成の場合は仕掛高となります。

総合原価計算
総合原価計算は、同じ種類の製品を連続して生産する場合に用いられ、大別すると次の3つの計算方法に分けることができます。なお、総合原価計算では、製造原価から、製作中の製品の原価(仕掛品原価)を差し引いた残りが完成品原価となります。
| 種類 | 対象となる生産形態 |
| ①単純総合原価計算 | 同じ種類の製品を連続して生産する場合に適用する |
| ②等級別総合原価計算 | 同じ種類の製品を連続して生産するが、製品を形状、大きさ、品位等によって区別する場合に適用する |
| ③組別総合原価計算 | 異なる種類の製品を組別に連続して生産する場合に適用する |
なお、製品が複数の製造工程により連続して生産される場合、上記①~③の総合原価計算方法を製造工程別に行うことができます。製造工程ごとに原価計算を行う方法を「工程別総合原価計算」といいます。